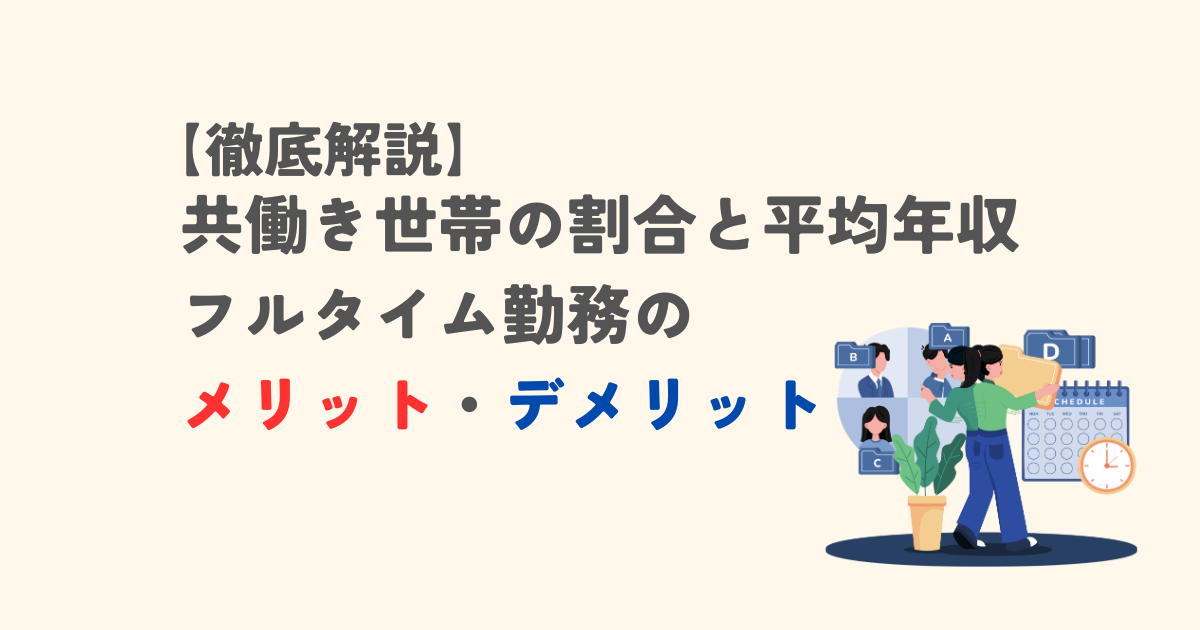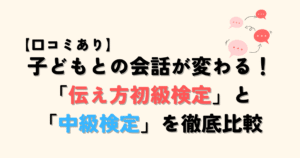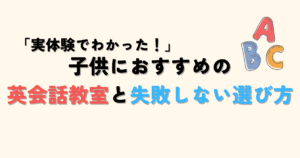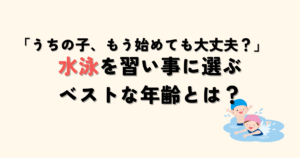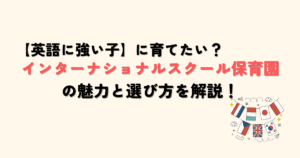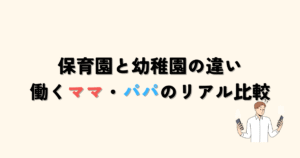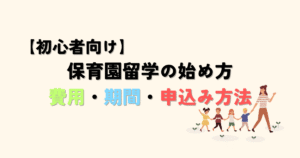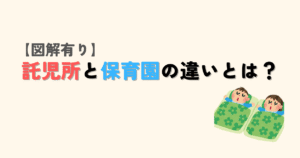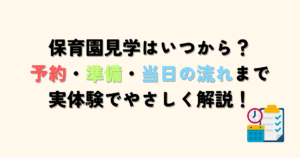最近、「周りの家庭もほとんど共働きになったな」と感じたことはありませんか?
実際、日本ではこの40年間で共働き世帯が大きく増加し、今では夫婦世帯の約7割を占めています(総務省「労働力調査2024年」)。
なかでもフルタイム勤務を続ける夫婦は、経済的な安定や将来の資金づくりに有利ですが、同時に家事・育児の時間不足といった悩みも抱えがちです。
この記事では、2025年最新の統計データをもとに、
- 共働きと片働きの年収の差
- 子どもの有無や人数別の年収傾向
- 共働きのメリットとデメリット
をわかりやすく解説します。
数字だけでなく、日々の生活に直結するポイントも交えて紹介しますので、
「これから共働きを続けるべきか迷っている」
「世帯年収を正しく把握して家計を見直したい」
そんな方の参考になるはずです。
目次
世帯年収の基礎知識
まず、「世帯年収」という言葉の意味を整理しましょう。
世帯年収とは、同じ家に住む家族全員の年間収入を合計した金額のことです。給与や賞与だけでなく、事業収入や年金、利子・配当収入なども含まれます。
平均値と中央値の違い
統計を見るときは「平均値」と「中央値」の違いに注意が必要です。
- 平均値:すべての世帯の年収を合計し、世帯数で割ったもの
- 中央値:年収順に並べたとき、ちょうど真ん中に位置する値
例えば、5つの世帯の年収が300万円・400万円・500万円・800万円・2000万円
だった場合、
- 平均値は(300+400+500+800+2000)÷5 = 800万円
- 中央値は500万円
平均値は高収入世帯に引き上げられやすい一方、中央値は「真ん中の家庭」の状況を表すため、実感に近い数字になります。
家計や将来設計を考える際は、平均値だけでなく中央値もチェックすることが大切です。
最新データ:共働き vs 片働きの年収比較(2025年版)
総務省「家計調査2024年」によると、夫婦と子ども1〜2人の世帯を比較すると、共働き世帯の平均実収入は約770万円、片働き(夫のみ就業)世帯は約580万円です。差額はおよそ190万円で、月額にすると約16万円の差になります。
この年収差は、以下の要因によって生じます。
- 妻の給与所得がそのままプラスされる
- 賞与や手当などの受給機会が増える
- 社会保険の加入状況による年金額・保障額の差
また、平均だけでなく中央値を見ても、共働き世帯は約700万円、片働き世帯は約550万円と、やはり150万円前後の差が存在します。
ただし、収入が増える一方で、共働きは保育料や外食費、家事外注費などの支出も増加しやすい傾向があります。したがって、年収差を「そのまま生活のゆとり」と考えるのは早計です。家計全体の収支バランスを見極めることが重要です。
出典:総務省「家計調査2024年」
子どもの有無・人数別の世帯年収
総務省「家計調査2024年」のデータをもとに、夫婦の働き方と子どもの人数による世帯年収の違いを見てみましょう。
| 世帯構成 | 共働き平均年収 | 片働き平均年収 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 夫婦のみ | 約780万円 | 約620万円 | 保育料なし、生活費は比較的安定 |
| 子ども1人 | 約770万円 | 約580万円 | 保育料・教育費が発生、支出増 |
| 子ども2人 | 約760万円 | 約560万円 | 教育費・食費・住宅費が大きく増加 |
子どもが増えると共働きでも年収はほぼ横ばい、あるいは微減する傾向があります。これは育児休業や時短勤務による収入減が一因です。
一方、片働きの場合は育児期間中も年収は大きく増えず、生活費負担が重くなります。
このデータから、子育て期間中に世帯収入を安定させるには、共働きのほうが有利であることがわかります。ただし、家事や育児の分担、勤務時間の調整をしないと、家計は安定しても家庭の疲労度が高まるリスクがあります。
出典:総務省「家計調査2024年」
リアルな家庭の働き方
- Aさん:保育園利用しながら働く家庭
子ども2人を育てる30代夫婦。共働きで世帯年収700万円。妻は時短勤務を利用し、夫は在宅勤務を週2回取り入れることで、保育園送迎を柔軟に分担。結果的に「子どもの急な発熱にも対応できた」との声。 - Bさん:外部サービスを積極活用する家庭
年収1,000万円を超える40代夫婦。高収入だが勤務時間も長いため、宅配食材や家事代行を導入。金銭的な余裕を「時間のゆとり」に変えることで、子どもとのコミュニケーションを増やせた。 - Cさん:片働きから共働きに切り替えた家庭
出産後しばらく専業主婦だったが、教育費を見据えて妻が復職。共働きにすることで収入が安定し、習い事や学資保険の加入も可能に。ただし時間管理は課題となり、夫婦で「家事分担表」を作成して乗り越えた。
共働きのメリット
共働きの最大の利点は、収入の安定と将来の資産形成のしやすさです。しかし、それだけではありません。長期的なキャリアや社会的な側面にもプラスの効果があります。
1. 収入の安定と生活の選択肢が広がる
共働き世帯は片働きに比べて年収が高く、教育費や住宅ローン返済、旅行や趣味などに充てられる余裕が生まれます。総務省のデータでは、その差は年間150〜190万円程度。家計にとっては大きなプラスです。
2. 将来の年金額が増える
妻がフルタイムや厚生年金加入のパートで働けば、将来の年金受給額も増えます。結果として、老後資金に余裕が出やすくなります。
3. キャリアを継続できる
出産や育児を経ても働き続けることで、昇進やスキルアップのチャンスを逃さずに済みます。ブランクが短いほど復職後の給与水準も保ちやすくなります。
4. 社会的つながりを保てる
職場や取引先との関わりが続くことで、社会との接点を持ち続けられます。特に育児期は孤立感を感じやすい時期ですが、働くことで気持ちの切り替えや交流の機会が得られます。
共働きのデメリット
収入面では有利な共働きですが、日常生活の中で感じる負担や不利な点もあります。これらを理解しておくことで、事前に対策を立てやすくなります。
1. 家事・育児の負担が増える
総務省「社会生活基本調査2021年」によれば、共働き世帯の平日家事・育児時間は妻が夫の2倍近くを担っており、特に未就学児がいる家庭ではその差が顕著です。時間的余裕が減ることで、精神的ストレスも蓄積しやすくなります。
2. 支出が増えやすい
保育料や延長保育料、外食・中食の利用増、家事代行サービスの利用など、働くことによって発生する支出があります。収入が増えても可処分所得は想定より少なくなるケースが多いです。
3. 税制・手当の対象外になることも
妻が一定以上の収入を得ると、配偶者控除や扶養手当の対象から外れます。結果的に税負担や社会保険料負担が増加します。
4. 夫婦間の時間が減る
双方が忙しいと、一緒に過ごす時間が減り、コミュニケーション不足が起きやすくなります。家族全体の満足度を下げないためには、意識的に「共有時間」を作る工夫が必要です。
共働きを見直す前のセルフチェック
共働きを選択する前に、以下のチェックをしてみましょう。
- 世帯年収に対して家計に余裕があるか
- 家事・育児の分担を夫婦で明文化しているか
- 税金・手当の変化(児童手当の所得制限など)を理解しているか
- 将来の教育費や住宅費を見越した貯蓄計画があるか
✔ すべてにチェックがつけば、安心して共働きを継続できるサインです。
まとめ:共働きの現状と向き合い方
今回の記事では、共働き世帯の割合や年収の最新データをもとに、メリット・デメリットを整理しました。
要点まとめ
- 共働き世帯は夫婦世帯の約7割
- 平均年収は片働きより150〜190万円高い
- メリットは収入安定・キャリア継続・年金額増加・社会的つながり
- デメリットは家事・育児負担増、支出増、税制面での不利、夫婦間の時間不足
- 成功の鍵は家事分担・時間管理・夫婦間のコミュニケーション
共働きは経済的な面で魅力がある一方、時間や体力の使い方に課題が残ります。
「働き方」と「家庭の過ごし方」をセットで考えることが、長く無理なく続けるためのポイントです。
関連記事
- 〖簡単3分〗育児時短就業給付金の申請手順と必要書類まとめ
→ 共働きで利用できる制度を知っておくと安心です。 - 〖図解有り〗託児所と保育園の違いとは?基本をやさしく解説
→ 子どもを預ける選択肢を理解しておくと、家庭の働き方の幅が広がります。